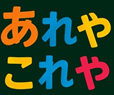自分が他界するとき遺族は何をすべきかをまとめてみた。
一般論
臨終とは、死を迎える間際の状態、または人が亡くなる瞬間を指します。医療機関において臨終を迎える際に行われることは以下の通りです。
危篤状況の連絡と末期の見守り
医師から危篤であると診断された場合、医療機関は家族や親しい人々に連絡を入れるよう促します。危篤状態は、病状が非常に深刻で生命の危険が高い状態であり、回復の見込みが薄いと判断されるためです。
家族や親しい人々は、患者が最期を穏やかに過ごせるように見守ることが重要です。手を握ったり、話しかけたりすることで、最期の時を共に過ごし、心の準備をすることができます。
死亡確認と死亡診断書の発行
患者が臨終を迎えると、医師による死亡確認が行われます。
死亡確認では、心臓の拍動停止、呼吸停止、瞳孔散大および対光反射の消失の3点が確認されます。
これらの確認がされると、医師は法的な死亡を証明する重要な書類である死亡診断書を発行します。死亡診断書は、死亡届や火葬許可証の取得に必要な書類となります。
死後処置(エンゼルケア)
死亡確認後、病院のスタッフ(看護師など)が故人の身体を清める「エンゼルケア(清拭)」を行います。
エンゼルケアでは、故人の身体をお湯やアルコールで拭き清め、耳や鼻に綿を詰めるほか、傷口などをカバーし、化粧を施して身なりを整えます。これは、故人の尊厳を守り、遺族の心のケアをする意味合いもあります。
清拭後は、白装束や故人の好きだった服に着替えさせることもあります。この処置は、死後硬直が始まる前の、死後2時間以内に行うのが理想的です。
末期の水(まつごのみず)
臨終直後には、「末期の水」という儀式を行うことがあります。これは、故人があの世で渇きに苦しまないようにという願いを込めて、故人の唇を水で湿らせる仏教の儀礼です。通常、病院側で準備してくれます。
臨終を迎える際には、このように医療機関が様々な処置や手続きをサポートしてくれますが、大切な方を見送る遺族の心構えも重要です。悲しみに暮れる中でも、死亡診断書の受け取り、死亡届や埋火葬許可申請の提出といった手続きが待っています。これらの手続きは、葬儀社に代理で行ってもらうことも可能です。
【0】【在宅看取り:本人が危篤と思われたときから臨終直前までの遺族の行動ガイド】
◆【第0章】「いよいよかもしれない」と感じたら
- 表情が虚ろ、反応が鈍い、呼吸が浅くなる、血圧や脈が弱まる
- 尿が減少、手足が冷たい、意識が混濁するなど
➡ この段階で、以下の準備を始めよう:
◆【第1章】訪問診療医との連携と対応
1-1. まず訪問医に連絡する(緊急時用番号を確認しておく)
- 「今の様子が通常と違う」「呼吸が苦しそう」など、簡潔に伝える
- 夜間や休日でも、訪問医の指示を仰ぐ(在宅看取り契約があれば対応可)
1-2. 訪問医師の対応
- 状況に応じて緊急訪問(看取り準備・点滴・苦痛緩和処置など)
- 診断内容の説明(死期が近いことの説明もあり得る)
1-3. 事前確認すべきこと
- 在宅看取りの同意書提出済みか(書面で用意されている)
- 死亡診断書の発行について:在宅で死亡した場合、訪問医が作成
- 医師の連絡先・緊急連絡先はメモして冷蔵庫や玄関に貼っておくと良い
◆【第2章】臨終が迫ったときの遺族の準備
2-1. 同居家族でできる準備
- できるだけ穏やかに付き添い、声をかける(意識がなくても聴覚は残る可能性)
- 不要な音・照明を落とし、静かな空間に
- 本人が望んでいた音楽、香り、好きだったものを近くに
2-2. すぐに連絡しておく人
- 訪問看護師・ケアマネジャー(利用している場合)
- 緊急連絡リストを確認:配偶者・子・きょうだいなど最低限に
例文(電話):
「○○が今、かなり状態が悪く、先生の話では今夜が峠とのことです。心の準備だけお願いします。」
【1】死亡直後にやるべきこと(〜24時間以内)
▸ 医師による死亡確認・死亡診断書の取得
- 病院で亡くなった場合は病院が発行。
- 自宅で亡くなった場合はかかりつけ医や救急医の診断。
▸ 家族・親族・関係者への連絡
- 妻や子ども(長女・長男)が主に行う。
- 連絡先リストがあると便利。
▸ 葬儀社への連絡
- 事前に依頼する葬儀社を決めておくと安心。
- 遺体搬送・安置場所の確保が必要。
【2】葬儀の準備と実施(2日〜1週間程度)
▸ 葬儀内容の決定
- 宗教形式(仏式、神式、キリスト教式、無宗教など)
- 葬儀の規模や場所(自宅・会館)
▸ 役所への届出
- 死亡届(死亡診断書とセット)を提出 → 火葬許可証の取得
▸ 火葬・納骨の手配
- 火葬場予約、遺骨の保管や納骨先の選定
【3】葬儀後すぐに必要な手続き(1週間〜1ヶ月)
▸ 役所・年金・保険関係の手続き
- 健康保険証の返却
- 国民年金・厚生年金の停止、遺族年金申請
- 介護保険の資格喪失届
▸ 銀行口座の凍結確認と対応
- 凍結される前に必要な出金は注意
- 凍結後は遺産分割協議書が必要
▸ 公共料金など名義変更
- 電気・ガス・水道・電話・携帯・インターネット・新聞など
【4】相続・遺産関連の手続き(1ヶ月〜10ヶ月以内)
▸ 遺言書の確認(有無)
- 公正証書遺言があれば家庭裁判所手続き不要
▸ 相続人の確認
- 法定相続人の確定(配偶者+子供)
▸ 遺産の把握
- 預金、不動産、有価証券、借金、車、保険などを整理
▸ 遺産分割協議と書類作成
- 相続人全員で合意し書面作成
▸ 相続税の申告(必要な場合)
- 原則として死亡から10ヶ月以内
【5】中長期的な対応
▸ 四十九日・一周忌などの法要
- 仏教の場合、節目の供養
▸ 名義変更・解約処理の続き
- クレジットカード、会員サービス、Webアカウント、SNSなど
▸ 家財や遺品整理
- 不要品処分、形見分けなど
【6】事前に本人が準備しておくとよいもの(生前)
- 連絡先リスト(家族・親戚・友人)
- 遺言書の作成(できれば公正証書)
- エンディングノート
- 銀行・証券・保険の一覧
- 葬儀や納骨に関する希望
- パスワード管理(PC・スマホ・ネットサービス)
📋 準備しておくとよいこと(ご家族向け)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 診療内容・看取りの可否 | 各クリニックごとに終末期の対応可否を確認 |
| 緊急連絡・対応体制 | 24時間365日対応があるか、電話の番号を控える |
| 訪問エリア | 居住地全域をカバーしているか確認 |
| 初回往診の流れ・費用 | 登録や初診、同意書、月2回訪問などルールを確認 |
🗺 どこに依頼すればよいか?おすすめの選び方
- 終末期医療・看取り対応の有無をクリニックサイトや問い合わせで確認
- 24時間緊急往診体制があるかをチェック
- 訪問可能エリアがご自宅を含むか確認
- 費用・同意手続き・初診スケジュールを家族で共有
在宅診療の診療報酬は、訪問診療の回数や患者さんの状況、医療機関の種類などによって異なります。一般的に、外来診療よりも高い単価が設定されており、同一建物居住者以外の場合、在宅患者訪問診療料1は1日あたり888点、在宅患者訪問診療料2は1日あたり884点です。同一建物居住者の場合は、それぞれ213点と187点になります。
詳細:
- 診療報酬の計算:診療報酬は、点数と単価を掛けて計算されます。1点は10円に換算されるため、例えば888点であれば8,880円となります.
- 負担金額:医療保険の自己負担割合によって異なりますが、例えば1割負担の場合、1ヶ月に2回の訪問診療で7,000円程度、3割負担の場合は20,000円程度が目安となります。
- その他:在宅療養支援病院(支援診1・2)や、在宅移行早期加算、包括的支援加算、頻回訪問加算などの加算も収益に影響します.